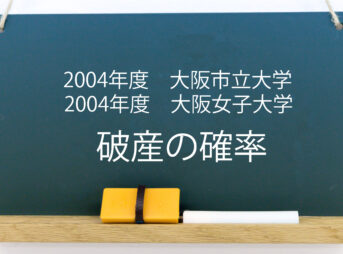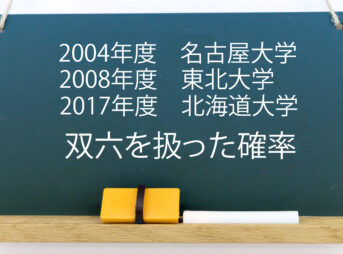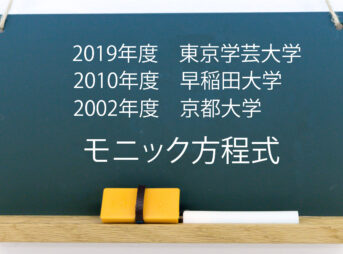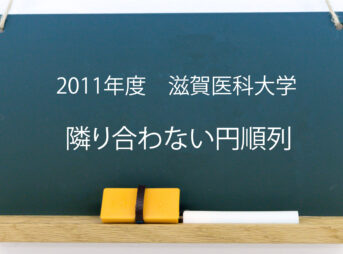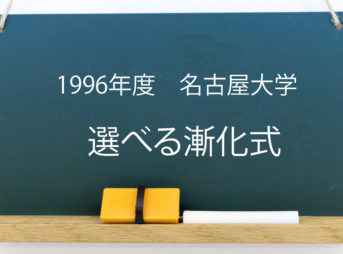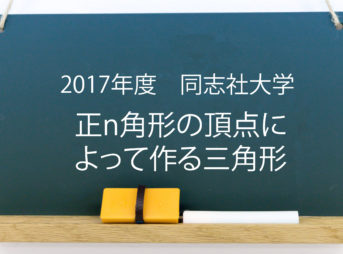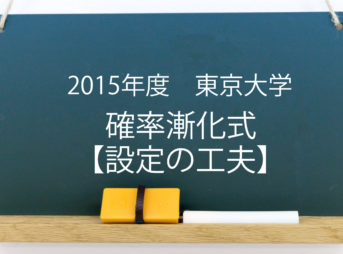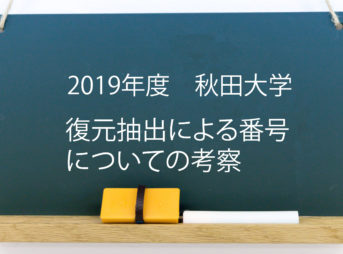1/n乗の対数の極限【logの服を着せる】【1991年度 北海道大学ほか】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 今回の話題は \(\displaystyle\frac{1}{n}\)乗の対数の極限 です。 昔 \(\displaystyle\frac{1}{3}\) の純情な感情 という曲がありました。 響きが似ていますね。 これが言いたかっただけです。 今回の話題は個人的に壊れるほど愛しているのですが、\(\displaystyle\frac{1}{3}\) も伝わればいいなと思います。 今のくだりが \(\displaystyle\f ...
破産の確率【初見ではほぼ絶望】【2004年度 大阪市立大学ほか】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 破産の確率と呼ばれるタイプの問題で、初見で解ききることは極めて困難です。 (1)、(2) は回数制限があるため、具体的に状態推移を追っていくことが可能です。 実際に(1)、(2) についてはできれば確保したいですが、筋が悪いと右往左往しかねません。 (以下ネタバレ注意) + クリック(タップ)して続きを読む (3)が今回話題の「破産の確率」です。 普通に考えると埒があきません。 直接計算で追うことは難しいので、漸化式を導入します ...
確率漸化式【ドロップアウト型~じゃんけん~】【2013年度 名古屋大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) じゃんけんを扱った問題です。 今回のゲームがもつ構造を私は 「ドロップアウト構造」 と呼んでいます。 今回だと3人からスタートして 3人 → 3人 → 3人 → \(\cdots\) → 2 人 → 2 人 → \(\cdots\) → 2 人 → \(\cdots\) というようにどんどん脱落していくような構造です。 じゃんけんはドロップアウト構造の典型例です。 実はじゃんけんに限らず、このドロップアウト構造をも ...
双六を扱った確率【ピッタリあがり】【超えたらあがり】【2004年度 名古屋大学ほか】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 難関大学では、有名なゲームをネタにしたような出題が時折出題されます。 本問は双六をモデル化した問題です。 答えを出す難しさというよりも、的確な表現で紙面上に記述する難しさがあるかもしれません。 表現力も問われてくると思います。 (以下ネタバレ注意) + クリック(タップ)して続きを読む 結局、2 ~ 7 というリーチゾーンの場所にいるならば毎回毎回 確率 \(\displaystyle \frac{1}{6}\) ...
モニック方程式【最高次が1である高次方程式】【2019年度 東京学芸大学ほか】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 最高次の係数が 1 であるような整数係数 \(n\) 次方程式を \(n\) 次のモニック多項式と呼びます。 入試においては名前まで無理に覚える必要はありませんが、名前がついているものについては 「あ~、モニック方程式の話題ね」 みたいに、シナリオやストーリーを端的にキーワードとして頭に整理しておけるというメリットがあると思います。 モニック方程式は独特な流れとシナリオがあります。 中には知らなきゃ厳しいという内容の式変形を要求 ...
隣り合わない円順列【極限との総合問題】【2011年度 滋賀医科大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 円順列を題材として、最後は極限の計算技能まで見る欲張りな問題です。(実践演習としては誉め言葉です。) 円順列の基本は 円順列のポイント 誰か一人の目から見る ということです。 公式 \(n\) 人を円形に並べる方法は \((n-1)!\) 通り がありますが、この「\(-1\)」というのはまさに「誰か一人の目から見て残りの \(n-1\) 人がどうなっているかが問題である」という現れです。 式の形に意味付けができれば、覚える(頭 ...
選べる漸化式【分析力や構想力を試す良問】【1996年度 名古屋大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 機械的な態度になりがちな漸化式の問題の中で、分析力や構想力を要する良問です。 個性の強さゆえ、一度ネタバレすると新鮮味は薄れます。 初見の方はぜひ限界まで考え抜いてほしいと思います。 (以下ネタバレ注意) + クリック(タップ)して続きを読む \(a_{1}+a_{2}+\cdots+a_{n}=S_{n}\) とおきます。 \(S_{n}=(a_{n}+\displaystyle \frac{1}{4})^{2} ...
正n角形の頂点によって作る三角形【2017年度 同志社大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) この手の問題は多くの問題集などにも収録されており、一度は経験したことのある人も多いでしょう。 また、正六角形や正八角形など、具体的な問題はやったことがあるという人も多いでしょうが、一般論として考えたことがある人はそこまで多くないのではないかなと思います。 具体的な問題の場合、「具体的だからこそできる解法」が収録されていることも多く、今回一般論で考えてみることにより、この手の問題について一度整理してみてほしいと思います。 少なくと ...
確率漸化式【設定する上での工夫】【2015年度 東京大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 確率漸化式の標準問題の多くは、基本的な漸化式の処理力があれば、どちらかというと得点源になる分野です。 本問の場合、機械的な態度になりがちなこの分野の問題において、思考要素を含む問題であり、面白い良問だと思います。 確率の問題では 漸化式を導入するかどうか ということは、方針決定において非常に大きな選択です。 通常の問題であれば、 「~~の確率を \(p_{n}\) とおく」 「\(p_{n+1}\) を \(p_{n}\) ...
復元抽出による番号についての考察【2019年度 秋田大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 復元抽出(元に戻して取り出す)について扱う問題です。 今回は箱から番号付きのカードを取り出すという設定ですが、サイコロを振るということについてもある意味復元抽出と同じと見なすことができます。 サイコロを振るのも、箱から1~6の番号付きのカードを元に戻しながら取り出すのも同じことですから。 そういった意味で、目先のカードだのサイコロだのにとらわれることなく、復元抽出という大きな括りでの話題だと整理しておき、いざ出題されたときは判断 ...