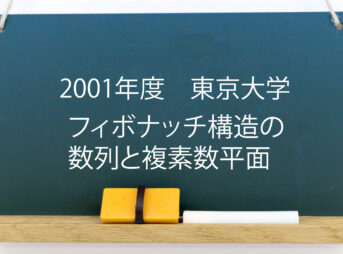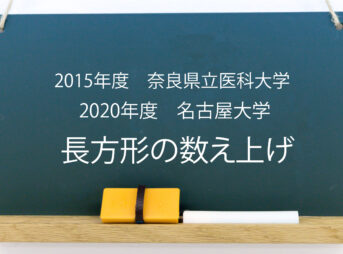漸化式の解法基本パターン 第5講【2項間漸化式:そうだ、logをとろう型】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) このシリーズの一覧はこちら 漸化式の解法基本パターン第5講では そうだ、log をとろう型 \(a_{n+1}^{p}=Aa_{n}^{q}\) というタイプを扱います。 両辺底が \(A\) の対数をとると \(p\log_{A}a_{n+1}=q\log_{A}a_{n}+1\) となり、\(b_{n}=\log_{A}a_{n}\) とおくと \(b_{n+1}=\displaystyle \frac{q}{p}b_{n} ...
漸化式の解法基本パターン 第4講【2項間漸化式:特性方程式使うと事故る型】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) このシリーズの一覧はこちら 漸化式の解法基本パターン第4講では 特性方程式使うと事故る型 \(a_{n+1}=pa_{n}+An+B\) というタイプをやっていきます。 長ったらしいネーミングですが、逆に一回事故った方が理解が深まると思います。 (もっといいネーミングがあれば募集します。) 文字のままやっててもピンとこないかもしれませんので、本問の (1) を例にとって、敢えて事故ってみます。 誤答 ...
漸化式の解法基本パターン 第3講【2項間漸化式:分数型】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) このシリーズの一覧はこちら 漸化式基本パターン第3講では、「分数型」の漸化式を扱います。 まずは分数型の中でも簡単な形(特殊な形)である 分数漸化式(メタボ型) \(a_{n+1}=\displaystyle \frac{ra_{n}}{pa_{n}+q}\) を考えます。 分数の形がなんとなく△の形をしており、引き締まっておりません。 逆数を取ると \(\displaystyle \frac{1}{a_{n+1}}=\disp ...
漸化式の解法基本パターン 第2講【2項間漸化式:心霊写真型】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) このシリーズの一覧はこちら 前回の第1講で扱った Type 1 \(a_{n+1}=pa_{n}+q\) ( \(p \neq 1\) ) の派生形として今回は Type 2 (心霊写真型) \(a_{n+1}=pa_{n}+q^{n}\) ( \(p \neq 1\) ) ( \(q\) の肩になんか乗ってる ) というタイプを扱います。 この心霊写真型の除霊の仕方は2パターンあり 心霊写真型の除霊の仕方 ...
漸化式の解法基本パターン 第1講【2項間漸化式:ズラせば等比数列】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 漸化式は問題を解く中で処理しなければならない場面が多々あります。 確率漸化式などの確率や場合の数の分野との融合 点列など、座標との融合 整数問題との融合 など、漸化式は道具として使う場面が多々あります。 漸化式が立式できても、それが解けないとなると意味がありませんから、基本的な漸化式についてはきちんと処理できる必要があります。 そこで基本的な漸化式について一通りこのシリーズで押さえておきたいと思います このシリーズの一覧はこちら ...
仮想難関大(オリジナル予想問題)【フィボナッチ数列を係数にもつ2次方程式の解】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 仮想難関大シリーズということで、東大、京大をはじめとする旧帝大、東工大、国公立大学医学部医学科などの難関国公立大を想定したオリジナルの自作問題です。 「手垢の付いていない問題で力試しがしたい」 という方はぜひご活用ください。 今回はフィボナッチ数列をテーマにした問題です。 (以下ネタバレ注意) + クリック(タップ)して続きを読む 元々は カッシーニ・シムソンの定理 \(f_{1}=f_{2}=1\) という条件の下で \(f_ ...
フィボナッチ構造の数列と複素数平面【2001年度 東京大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 一見何かあるのだろうかと疑わせるような設定です。 フィボナッチ構造が見える分、何かあるのか?と疑ってしまいますね。 注意 厳密には、\(f_{1}=f_{2}=1 \ , \ f_{n+2}=f_{n+1}+f_{n}\) と初期条件が 1 , 1 であるものをフィボナッチ数列と呼びます。 今回は初項が違うので「フィボナッチ構造」という呼び方をすることにします。 東大は一見して、「何かあるのか?」と思わせるような出題がよくあります。 た ...
2021年度 北海道大学理系第4問【連立漸化式と整数問題】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 連立漸化式をベースとした整数問題であり、ざっと見た感じだと 「証明のベースは漸化式と相性の良い数学的帰納法かな。全貌に関しては手を動かしてみないと分からんな。」 という印象でした。 (1) は計算するだけなので、問題はないでしょう。 (2) ですが、 \(a_{n}\) が常に偶数なのか、\(b_{n}\) が常に偶数なのか、時と場合によって違うのか という疑問のもと、実験して様子を掴んでみようと思いました。 実験の結果、\(a_{n}\) ...
2021年度 名古屋大学理系第4問【ガウス記号を含む漸化式】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) ガウス記号に関する問題で、見かけに圧倒されて深入りしなかった受験生も少なくないかと思われます。 一般に \([x]\) に対して , ガウス記号に関する不等式 \(x-1 \lt [x] \leq x\) \(\cdots\) ① あるいは \([x] \leq x \lt [x]+1\) \(\cdots\) ② という不等式を駆使しながら話を進めていきます。 ① から ② が導けますし、② から ① が導けます。 覚 ...
長方形の数え上げ【階段状の図形内の長方形の個数】【2015年度 奈良県立医科大】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 非常にシンプルな問題で、どことなく「何かうまい方法でできそう」みたいな匂いを感じます。 大学入試と言うよりはむしろパズル的な問題に感じる人もいるかもしれません。 時間に余裕がある家での勉強において、あぁでもない、こうでもないと試行錯誤する分にはいいのですが、試験場だと頭に血が昇ってしまいやすいでしょう。 本問はどちらかと言うと地道に数え上げていく方針と、閃き一発で終了する方針とが考えられます。 試験場であればこっちの解答かなと思 ...