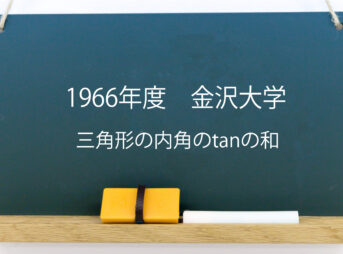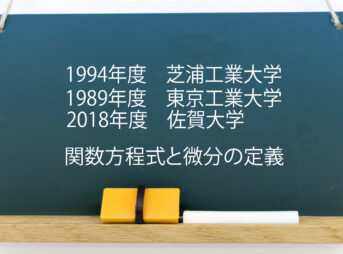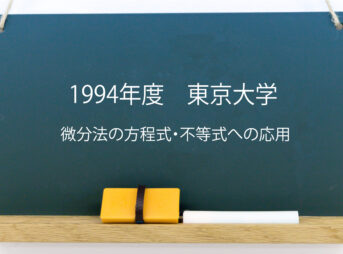2022年度 北海道大学 理系第3問【不等式で表される領域と面積】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 不等式で表される領域と、面積に関する問題です。 方向性自体は割と一本道で、迷うことはありませんが、それを処理しきるためには 「見るべき部分を見る」 ということが必要になってきます。 不必要な部分にとらわれすぎてしまい、身動きがとれなくなってしまう恐れは多々あります。 一つ一つの処理で特別なことはしていませんが、「やり方」に終始して根本的な部分を蔑ろにしてきた受験生からすると、 「聞けば分かる」 で終わってしまいます。 本番の入試で「聞けば分か ...
2022年度 東北大学 理系第3問【不等式証明とはさみうちの原理】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 不等式証明からの、はさみうちの原理という流れ自体はパッと見で読み取れるでしょう。 ただ、(1) の不等式証明は 聞けば簡単だが、意外と単純ではない という問題で、案外バカにはできません。 腕力で押し切ることも可能ですが、工夫の余地はあります。 そのあたりは【解1】【解2】【解3】あたりでご確認ください。 (2) は (1) で証明した不等式を用いてはさみうちの原理で仕留めるんだろうな 形的に区分求積法が狙えそうだな ということになることは予見 ...
2022年度 東北大学 理系第2問【4次関数の極値と最小値】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 4次関数に関する極値や最小値に関して考える問題です。 パッと見の印象はそこまで怖そうではありませんが、 手を進めていくうちに段々と血の気が引いていく という感覚になっていくでしょう。 まともにぶつかるとなると相当ツライ処理を強いられます。 見るべき部分があっちにいったりこっちにいったりと、目線の移動も激しく強靭な整理力や把握力も求められます。 現実的に処理しきるためには計算上の工夫もある程度必要です。 相当厳しい問題ですが、 \(f(x)\) ...
2022年度 東京大学理系第4問【全称命題と存在命題】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 3次関数についての性質について論じる問題ですが、 全称命題 任意の○○に対して△△が成立する 存在命題 ある○○が存在して☆☆が成立する というような 全称命題、存在命題 を真正面から扱うことになります。 ひとまず出題者との会話のキャッチボールができるかどうかという部分でのフィルターとしてはたらくことになるでしょう。 また、 感覚的に「そりゃそうだろ」 とか、 「この部分直感的に処理しちゃいたいな」 というようなことが多々あるのですが、それを ...
2022年度 東京大学理系第3問【定義の運用】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 「十分離れている」という言葉を定義し、その定義に関して何が言えるのか、どうなっていればよいのかを考えさせるという その場力 を要求している問題です。 ソーシャルディスタンスを意識したような用語だなと感じました。 解き終わってみると、特別難しいわけでもなく、計算量自体もそこまで多くはないのですが 様子を掴んだり状況を把握するのにエネルギーを使う と思います。 問題自体の難易度と、試験場での体感難易度には大きなギャップがあるでしょう。 問題自体の ...
2022年度 東京大学理系第1問【微分法による最小値の導出】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 微分法により、関数の最小値を導出するという基本問題です。 インテグラルを含んだままの関数ですから、最後の最小値の導出にあたっては積分計算についても問われることになります。 やることが明確であるため、方針面で迷うことはないでしょうし、計算の内容や計算量についても標準レベルと言ってよい穏やかなレベルです。 それだけに試験場では確保したい問題と言えましょう。 解答はコチラ
三角形の内角のtanの和【1966年度 金沢大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 非常にシンプルな問題です。 切れ味鋭く捌くこともできますし、腕力で押し切ることもできます。 いずれの路線にせよ、確かな力が必要です。 類題としては などがあります。 原題では誘導設問がついていましたが、それだと面白くなくなってしまうのと、誘導がなくても現実的に処理可能であるということ、試験問題ではなく教材としての提供であることを考え心を鬼にして誘導をカットしました。 ぜひ構想を含めて手を動かしながら考えてみてほしいと思います。 (以下ネタバレ ...
関数方程式と微分の定義【1994年度 芝浦工業大学ほか】
例題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 関数方程式の問題で、最終的には微分方程式に帰着するタイプです。 場数を踏むことで、このトピックスに対する勘所を掴んでいきましょう。 (以下ネタバレ注意) + クリック(タップ)して続きを読む (1) について 与えられた手持ちの武器は \(f(x+y)+f(x)f(y)=f(x)+f(y)\) という式しかなく、具体的に \(f(x)\) が与えられているというわけではありません。 この等式から \(f(0)\) に辿り着くために、 特殊な値 ...
微分法の方程式・不等式への応用【1994年度 東京大学】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 見た目は、どこにでもありそうな微分の運用問題のように思えます。 ただ、型通りの問題で終わらないよう、言葉にすることが難しい「センス」を要求してくるあたりが流石東大です。 本問は1994年度東京大学理系第1問です。 「これはテンプレ問題だ。いける」 と試験開始直後に意気揚々と取り組み始め、計算量の多さに血の気が引いていく当時の受験生の様子が目に浮かびます。 第1問という位置取りも相まって、平常心を失いかねない問題と言えましょう。 (以下ネタバレ ...
仮想難関大(オリジナル予想問題)【微分法~大小比較~】
問題はこちら(画像をクリックするとPDFファイルで開きます。) 仮想難関大シリーズということで、東大、京大をはじめとする旧帝大、東工大、国公立大学医学部医学科などの難関国公立大を想定したオリジナルの自作問題です。 「手垢の付いていない問題で力試しがしたい」 という方はぜひご活用ください。 今回は微分法に関する問題です。 \(a^{b}\) と \(b^{a}\) という形の2数についての大小比較がテーマです。 古くからある有名問題であり、(1) , (2) までは定番の内容です。 (3) で少し「ムムっ ...